Web反響ラボ
ホームページ制作・WEB制作 | 福岡・北九州
Google検索「ホームページ制作 福岡」「ホームページ制作 北九州」上位表示中!
093-982-4223
平日 9:30 - 17:30
福岡県北九州市小倉南区星和台2丁目2-36-2
- 投稿日
- 最終更新日
初心者必見!Google広告の仕組みと広告が表示される基準
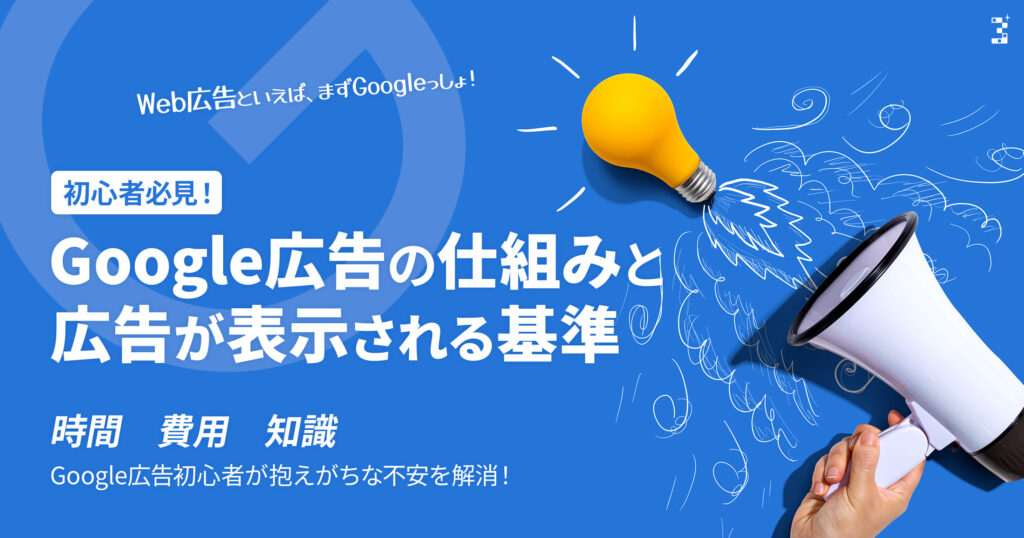
「Google広告を使ってもっと集客を増やしたい」「事業を成長させたい」と思う一方で、Google広告の効果や仕組みに関して、不安や悩みを抱えているのではないでしょうか。
確かに、限られた予算の中で最大限の効果を求める中小企業や個人事業主の方にとって、広告出稿は大きな決断です。
そこで当記事では、Google広告初心者が抱えがちな不安(時間、費用、知識)の解消を目指します。
この記事を最後まで読めば、Google広告の「仕組み」が理解でき、無駄な広告費を抑えつつ着実に集客を成功させるための具体的な道筋が見えるはずです。
もし、この記事を読んでも不安が残る、あるいは専門家のサポートを受けながら最短で成果を出したいとお考えなら、ぜひ一度当社の無料相談をご利用ください。
あなたのビジネスに最適な広告戦略を一緒に考えます。
目次 - Index -
18544文字
読み終わる時間の目安:約31分
第1部:Google広告の「仕組み」を解説:初心者でも分かる3つの重要ポイント
複雑に見えるGoogle広告ですが、その仕組みの根幹は、実は3つの重要なポイントに集約されています。
- ユーザーとビジネスを繋ぐ「マッチングシステム」
- 「入札単価」と「広告ランク」の関係性
- 「クリック課金」と予算の考え方
まずはこの3つを理解すれば、広告が表示される原理から費用が発生する仕組みまで、クリアになります。
では、その「3つの重要ポイント」を見てみましょう。
1.1 なぜ広告が表示される?ユーザーとビジネスを繋ぐ「マッチングシステム」
Google広告とは、一言で言えば「ユーザーが抱える悩みや欲求」と「あなたのビジネスが提供する解決策」を結びつける、広告のマッチングシステムです。
例えば、あるユーザーが「肩こり 解消 グッズ」と検索したとします。このとき、ユーザーは「肩こりを解消したい」という明確なニーズを持っています。一方で、あなたは肩こり解消グッズを販売しているビジネスオーナーだとします。Google広告の役割は、この両者を瞬時に結びつけ、検索結果画面にあなたの広告を表示することです。
ここで重要なのが、Googleが最も大切にしている思想、「ユーザーファースト」です。Googleの使命は、ユーザーに最も関連性が高く、役立つ情報を提供すること。これは、広告においても全く同じです。
なぜなら、ユーザーが広告をクリックして「期待外れだった」と感じる体験が続けば、ユーザーはGoogleを使わなくなります。人が集まらない場所に広告を掲載しても結果を得にくく、その結果広告主もいなくなり、Googleにとっても不利益となってしまうからです。
つまり、Googleは常に「この検索をしたユーザーにとって、どの広告が最も役に立つだろうか?」という視点で広告を選んでいます。この「ユーザーファースト」の思想が、次にお話しする「掲載順位の決まり方」の根幹をなしているのです。
1.2 掲載順位は「金額」だけじゃない!「入札単価」と「広告ランク」の関係性
多くの初心者が抱える誤解は、「広告の掲載順位は入札単価の高さだけで決まる」というものです。
これは、明確な間違いです。
正確に言うなら、以前はそうでしたが今は違います。
もし今もそうであれば、資金力のある大企業が常に上位を独占し、中小企業には勝ち目がなくなってしまいます。しかし、Googleはそうならないような、公平な仕組みを用意しています。それが「広告ランク」という考え方です。
広告の掲載順位は、この「広告ランク」のスコアが高い順に決まります。
そして広告ランクは、「入札単価」だけで決まるのではなく、広告と検索ワードの関連性なども加味されて決まるのです。
以下が、広告ランクの主な決定要因です。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 入札単価(Yourbid) | 広告主が設定するクリック単価の上限。 |
| 広告とランディングページの品質(AdQuality) | オークション時に測定される品質。これには推定クリック率、広告の関連性、ランディングページの利便性が含まれます。これらは入札ごとの状況を加味した評価です。 |
| 広告ランクの下限値(AdRankthresholds) | 広告を表示するために最低限必要な品質と入札単価の基準値。 |
| オークションの競争力(Competitivenessofanauction) | 他の広告主との競合状況。 |
| ユーザーの検索背景(Contextoftheperson’ssearch) | ユーザーの所在地、使用デバイス、検索時刻、検索語句の性質など、検索時のコンテキスト。 |
| 広告アセットやその他フォーマットの推定効果(Expectedimpactofassets) | サイトリンクや電話番号表示オプションなどのアセットが、広告のパフォーマンスに与える見込み効果。 |
(出典:広告ランクについて)
これは、Googleが単に「広告」を順位付けしているのではなく、「このユーザー、この瞬間にとって、最も価値のある広告体験はどれか」を判断していることを意味します。
資金力のある大企業が高い入札単価を設定しても、特定の地域や時間帯にいるユーザーにとって、より関連性の高いアセットを持つ中小企業の広告の方が高く評価され、上位に表示される可能性があるのです。
この点が、中小企業にとっての最大のチャンスとなります。
1.3 広告費はいつ、いくらかかる?「クリック課金」と予算の考え方
広告費がいつ、いくら発生するのかは、最も気になるポイントでしょう。
Google広告は、後払いか先払いかを選択できます。
後払い:クレジットカードを登録しておくことで、決められた課金額もしくは日数に達した段階で課金される。
先払い:PayPay残高払いや楽天Edy、Suicaのように事前にチャージして支払う(プリペイド)のと同じ仕組みで、まず先に広告予算をGoogleへ支払う。
そして、Google広告の最も基本的な課金方式は「クリック課金(CPC:Cost Per Click)」です。
これは、広告が何回表示されても(インプレッション)、費用は一切かからず、ユーザーが広告をクリックして初めて費用が発生する(チャージした金額から差し引かれる)仕組みです。これは掲載した広告に興味を持った可能性が高いユーザーに対してのみ、広告料金を払うことを意味しています。
では、広告予算はどのように考えればよいのでしょうか。多くの人が「とりあえず月々5万円で始めてみよう」といった形で、漠然と予算を決めてしまいがちです。しかし、目標から逆算して必要な予算を算出するという方法もあります。
具体的なステップは以下の通りです。
- 目標(ゴール)を明確にする
まず、「広告を通じて何を達成したいのか」を具体的に決めます。例えば、「月に10件の問い合わせを獲得する」といった形です。 - 目標CPA(顧客獲得単価)を決める
次に、「1件の成果(この場合は問い合わせ1件)に対して、いくらまでなら広告費を支払えるか」を決めます。これをCPA(Cost Per Acquisition)と呼びます。これは、あなたのビジネスの利益構造から算出します。例えば、1件の問い合わせから平均5万円の利益が生まれるなら、1件あたり1万円の広告費をかけても十分に採算が合います。この場合、目標CPAは1万円となります。 - 必要な広告予算を算出する
最後に、①と②を掛け合わせます。
必要な広告予算=目標コンバージョン数×目標CPA
先ほどの例で言えば、『10件×10,000円=100,000円』となり、月に10万円が、事業目標を達成するために必要な「投資額」として算出されます 。
この考え方の利点は、広告運用がビジネス目標と直結することです。もし、目標CPAの1万円以内で安定して問い合わせが獲得できると分かれば、「予算を20万円に増やせば、問い合わせも20件に増やせるのではないか?」という、事業拡大のシミュレーションが可能になります。広告費が、単なるコストではなく、売上をコントロールするための戦略的なレバーになるのです。
第2部:Google広告の種類を「目的別」に使い分ける
Google広告は「目的別に」使い分けましょう。顕在層にアプローチするには『検索キャンペーン』を、潜在層にアプローチするには『ディスプレイキャンペーン・動画キャンペーン』がおすすめです。
大切なのは、ビジネスの「目的」に合わせて、最適な広告のキャンペーン(種類)を選択することです。代表的な広告の種類を、「どんな顧客にアプローチしたいか」という視点で解説します。
2.1 顕在層にアプローチ!「いますぐ客」を集める検索キャンペーン
検索キャンペーン(一般的にリスティング広告と呼ばれるもの)は、Googleの検索結果ページに表示されるテキスト形式の広告です。
検索キャンペーンがアプローチするのは「顕在層」、つまり「いますぐ客」です。彼らは、自らの悩みや欲求を解決するために、具体的なキーワードで能動的に情報を探しています。例えば、「渋谷区 税理士 確定申告」と検索する人は、まさに今、税理士を探している可能性が非常に高い顧客です。
検索キャンペーンの最大のメリットは、このように購買意欲や利用意欲が非常に高いユーザーに、ピンポイントでアプローチできる点にあります。そのため、コンバージョン(商品購入や問い合わせなどの成果)に繋がりやすく、広告投資の回収が早いのが特徴です。
「少額予算から始めたい」「まずは確実に成果を出したい」という初心者の方にとって、検索キャンペーンは有効な選択肢になります。
2.2 潜在層にアプローチ!「認知」と「興味」を広げるディスプレイ・動画キャンペーン
ディスプレイキャンペーンや動画キャンペーンは、検索キャンペーンとは異なる層の顧客にアプローチするための広告です。
ディスプレイキャンペーンは、ニュースサイトやブログ、アプリといったGoogleの提携ネットワーク上の広告枠に、画像やバナー形式で広告を表示するものです。
動画キャンペーンは、主にYouTubeの動画再生前後や再生中に、動画形式の広告を配信します 。
ディスプレイキャンペーンや動画キャンペーンの広告がアプローチするのは「潜在層」です。彼らは、今すぐ商品やサービスを探しているわけではありません。しかし、彼らの興味・関心や過去の閲覧履歴などから、「将来的に顧客になる可能性がある」と判断された人々です。
例えば、普段からキャンプに関するブログをよく読んでいる人に対して、最新のアウトドアグッズのディスプレイ広告を表示したり、DIYの動画をよく見ている人に、電動工具の動画広告を見せたりする、といったアプローチです。
これらのキャンペーンの主な目的は、すぐに購入してもらうことではなく、まずは自社のブランドや商品を「知ってもらう(認知)」こと、そして「興味を持ってもらう(興味喚起)」ことです。将来の見込み客を育てるための、いわば「種まき」のような役割を担います。
検索キャンペーンで成果が安定してきた後の次のステップとして、あるいは新商品の認知度を一気に高めたいといった明確な目的がある場合に活用を検討すると良いでしょう。
2.3 【早見表】あなたの事業に最適な広告の種類は?
検索キャンペーン・ディスプレイキャンペーン・動画キャンペーンを、一目で比較できる早見表にまとめました。
ビジネスの目的と照らし合わせながら、どの広告から始めるべきかを確認してみてください。この表は、単に見やすくまとめただけではなく、広告戦略を決定するための重要な意思決定ツールとなるでしょう。まず「目的」の列を見て、ご自身の現状に最も近いものを選ぶことで、最適な広告タイプが自ずと見えてくるはずです。
| 目的 | 見込み客の獲得、販売促進、問い合わせ増加 | 認知度向上、ブランディング、リマーケティング | ブランディング、商品・サービスの理解促進 |
|---|---|---|---|
| 広告の種類 | 検索キャンペーン | ディスプレイキャンペーン | 動画キャンペーン |
| ターゲット層 | 顕在層(「いますぐ客」) | 潜在層(興味・関心、属性でターゲティング) | 潜在層(興味・関心、視聴習慣でターゲティング) |
| 広告形式 | テキスト | 画像、バナー | 動画 |
| 主な課金方式 | クリック課金(CPC) | 表示課金(CPM)またはクリック課金(CPC) | 視聴課金(CPV)または表示課金(CPM) |
| こんな事業に最適 | 緊急性の高いサービス(鍵修理など)、比較検討される商材(BtoB製品など)、指名検索される商品 | 新商品・新サービス、ビジュアルで魅力を伝えたい商材(アパレル、食品など)、幅広い層にリーチしたい事業 | ブランドストーリーを伝えたい事業、複雑な商品の機能を分かりやすく解説したい事業 |
第3部:【初心者必見】無駄な広告費をなくす運用の7つのポイント
Google広告の仕組みと種類を理解しただけでは、まだ成功への道のりは半分です。残りの半分は、日々の「運用」にあります。初心者が広告費を無駄にしてしまう原因の一つは、この運用段階でのつまずきにあります。
ここでは、失敗を未然に防ぎ、投資効果を最大化するための「7つの重要ポイント」に絞って解説します。
- 失敗はここで決まる!「LP」と「コンバージョン計測」の重要性(受け皿とゴール)
- 無駄なクリックを防ぐ「キーワード」と「マッチタイプ」の選び方(誰に見せるか)
- 除外キーワード設定(誰に見せないか)
- 広告文とランディングページの整合性(クリックの質を高める)
- 配信ターゲットの絞り込み(地域・時間帯・デバイスなど)
- 成果を出すための「改善サイクル」と運用体制の作り方(放置しない、データを見る)
- 成果指標(KPI)の明確化と入札戦略の理解
3.1 失敗はここで決まる!「LP」と「コンバージョン計測」の重要性(受け皿とゴール)
多くの初心者の方は、広告文やキーワード選定に注力してしまいますが、実は広告の成否を最終的に決定づけるのは、広告をクリックした後のユーザー行動です。具体的には、「ランディングページ」と「コンバージョン計測」の2つです。「ランディングページ」と「コンバージョン計測」は、広告運用の成功を支える土台であり、ここが疎かになっていると、広告効果が十分に発揮できません。
ランディングページの役割
ランディングページは、ユーザーが広告をクリックした際に、最初に表示されるWebページのことです。このランディングページの質が低いと、せっかく広告費をかけて集めた見込み客を、お問い合わせに繋げることができません。
成果の出るランディングページには、共通点があります。
- メッセージの一貫性:広告文で「初回限定50%オフ!」と謳っているなら、ランディングページの最も目立つ場所(ファーストビュー)に、同じメッセージが大きく表示されている必要があります 。広告とランディングページの内容が違うと、ユーザーは「話が違う」と感じ、離脱してしまいます。
- 明確なCTA(Call to Action:行動喚起):ユーザーに次に何をしてほしいのかを、大きく分かりやすいボタンで示すことが不可欠です。「無料で資料請求する」「今すぐ問い合わせる」といった具体的な文言で、迷わず行動できるように導きましょう。
- 信頼性の担保:ユーザーは、知らない企業から商品を買うことに不安を感じています。その不安を払拭するために、「お客様の声(写真付きだとさらに効果的)」「導入事例」「メディア掲載実績」といった客観的な証拠を提示し、安心感を与えることが重要です。
コンバージョン計測の重要性
コンバージョン計測とは、広告経由のユーザーが、あなたの定めたゴール(商品購入、問い合わせ完了など)に到達した数を正確に把握するための設定です。
これは、お店における「レジ」のようなものです。レジがなければ、どれだけお客さんが来て、何が売れたのか、把握できません。
つまり、コンバージョンデータがなければ、どのキーワードが成果に繋がり、どの広告文が効果的なのかを判断できません。これでは、改善のしようがありません。さらに重要なのは、Google広告のAI(機械学習)は、このコンバージョンデータを基に学習し、広告配信を最適化していく仕組みになっていることです。コンバージョン計測を設定しないと、AIは何も学習できず、いつまで経っても非効率な広告配信が続いてしまうのです。
設定は、サイトの「問い合わせ完了ページ」や「購入完了ページ」に「コンバージョンタグ」と呼ばれるコードを設置するのが基本です。少し専門的な作業に感じるかもしれませんが、これは広告費を投下する前に完了させなければならない優先事項の一つです。
3.2 無駄なクリックを防ぐ「キーワード」と「マッチタイプ」の選び方(誰に見せるか)
検索広告の費用対効果は、どのような「キーワード」で広告を表示させるかによって大きく左右されます。無駄なクリックを減らし、見込みの高いユーザーだけを集めるためには、「キーワードの意図」と「マッチタイプ」の理解が不可欠です。
キーワードの「意図」を見極める
ユーザーが検索するキーワードには、その裏にある「意図」が隠されています。例えば、同じ「英会話」というテーマでも、
- 「英会話 上達法」:情報を探している段階(情報収集意図)
- 「オンライン英会話 比較」:複数のサービスを比較検討している段階(比較検討意図)
- 「〇〇英会話 料金プラン」:特定のサービスへの申し込みを考えている段階(購買意図)
というように、意図が異なります。
限られた予算で成果を出すためには、より購買意欲の高い、具体的なキーワード(例:「サービス名+料金」「地域名+サービス名」など)から優先的に出稿していきます。
「マッチタイプ」で表示範囲をコントロールする
マッチタイプとは、登録したキーワードに対して、どの程度広い範囲の検索語句まで広告を表示させるかを設定する機能です。これは、Googleに対する「指示の厳しさ」を調整するようなものです。
| マッチタイプ | 記号 | キーワード例 | 表示される検索語句の例 | 戦略的用途 |
|---|---|---|---|---|
| 完全一致 | [ ] | [女性用帽子] | 女性用帽子,帽子女性用,婦人帽子(意味が完全に一致) | 登録したキーワードと全く同じ意味または意図の検索語句にのみ広告を表示。過去の実績からコンバージョンが確実に見込める「鉄板キーワード」に使用。予算を最も厳密に管理したい場合に最適です。 |
| フレーズ一致 | "" | "女性用帽子" | セール女性用帽子,青い女性用帽子,ニット帽女性用(キーワードの意味合いを含む) | 確度とリーチのバランスが取れたタイプ。意図しない検索を抑制しつつ、関連性の高い新たな検索語句を発見できます。2021年のアップデートで柔軟性が増し、使いやすさが向上しました。 |
| インテントマッチ | (なし) | 女性用帽子 | レディースキャップ,日よけハット購入,冬物ビーニー(関連性があれば表示) | リーチを最大化し、想定外の優良キーワードを発見するために使用します。コンバージョン計測が正確に設定され、AIに学習データを与える「スマート自動入札」との組み合わせが前提となります。 |
「フレーズ一致」と「完全一致」は表示範囲を絞り、確度の高いユーザーに確実に広告を届けることに向いています。一方でユーザーを絞る関係上、配信ボリュームはインテントマッチと比べて小さくなります。
「インテントマッチ」は、配信ボリュームを出しつつ一定の精度で配信することに向いています。ただし思わぬキーワードで広告が表示され、予算を浪費してしまうリスクがあります。
そのため、自社の状況に合わせて最適なマッチタイプを選択している戦略が重要なのです。
3.3 除外キーワード設定(誰に見せないか)
「誰に見せるか」と同じくらい重要なのが、「誰に広告を見せないか」です。無関係な検索に対して広告が表示されると、クリックされても成果に繋がらず、広告費の無駄遣いになります。それを防ぐのが「除外キーワード」の設定です。
無駄なクリックを未然に防ぐ「除外設定」
除外キーワードは、広告運用を始める前に、あらかじめ設定しておくのがおすすめです。
| 除外パターン | 除外キーワードの例 |
|---|---|
| 購入意欲が低いキーワード | 「無料」、「求人」、「やり方」、「とは」など |
| ビジネスに合わない言葉 | 高級店なら「安い」「中古」、BtoBサービスなら「個人」など。 |
定期的なパトロールで無駄を発見しよう
除外にあたるキーワードは、Google広告の「検索語句レポート」で確認できます。これは、実際にユーザーがどんな言葉で検索して広告が表示されたかを見られる一覧表です。
このレポートを見て、「当社の商品とは関係ないな」「この検索でクリックされても買わないだろうな」という言葉を見つけたら、除外キーワードに追加しましょう。この地道な作業が、後々のコスト削減に繋がります。
3.4 広告文とランディングページの整合性(クリックの質を高める)
ユーザーが検索したキーワードは広告文に存在し、広告文に記載されている内容は、ランディングページにも記載されているとより効果が見込めます。
例えば、広告文で「期間限定セール!」とアピールしているのに、ランディングページにセールの情報がどこにも書かれていなかったら、ユーザーは「話が違う」と思ってすぐにページを閉じてしまいます。この検索キーワードと広告文、ランディングページの不一致が、無駄な広告費とブランドイメージの低下を招きます。
広告で伝えた魅力や利点は、必ずランディングページの目立つ場所で、もう一度伝えましょう。
3.5 配信ターゲットの絞り込み(地域・時間帯・デバイスなど)
広告予算は無限ではありません。だからこそ、成果が出やすい場所に集中投資し、成果が出にくい場所への投資を減らす「選択と集中」が重要になります。
データを見て「勝ちパターン」を見つけよう
Google広告のレポートを見れば、どんな場所、時間、デバイスで成果が出ているかが一目瞭然です。
| 項目 | 分析例 | 対策例 |
|---|---|---|
| 地域 | 東京都からのコンバージョンが多い。逆に、成果が全く出ていない県がある。 | 東京都への配信を強化する。成果が出ていない県は配信対象から除外する。 |
| 時間帯 | BtoBサービスで、平日のビジネスタイムにしか問い合わせがない。 | 深夜や休日の配信を停止または弱めることで、無駄な支出を抑える。 |
| デバイス | パソコンからの購入率が高いのに、スマホからの購入率が極端に低い。 | スマホへの配信を弱める(またはランディングページをスマホ対応に改善する)。 |
分析結果に基づき、設定項目ごとの入札単価調整比を使い、入札単価を増減させます。
例えば、モバイルのコンバージョン率がパソコンの半分であれば、モバイルには-50%の入札単価調整を適用します。一方、パソコンが最も収益性が高い場合は、+25%の調整を適用することで、効率的な運用が可能になります。
その他の設定
やや専門的にはなりますが、以下のような設定項目でターゲットを絞ることも可能です。
| オーディエンスの種類 | 概要 | ターゲットユーザー |
|---|---|---|
| 検索広告向けリマーケティングリスト(RLSA) | 過去にWebサイトを訪れたユーザーをターゲットにする。 | 過去にWebサイトを訪問したユーザー |
| 類似オーディエンス | 既存のリマーケティングリストと類似した新規ユーザーのオーディエンスを作成する。 | 商品に興味を持つ可能性が高い新規顧客 |
| 購買意向の強いオーディエンスとアフィニティオーディエンス | Googleのデータに基づき、広告主の商品のような製品を積極的に調査しているユーザー(購買意向)や、特定のトピックに長期的な関心を持つユーザー(アフィニティ)をターゲットにする。 | 特定の製品を積極的に調査しているユーザー、または特定のトピックに長期的な関心を持つユーザー |
3.6 成果を出すための「改善サイクル」と運用体制の作り方(放置しない、データを見る)
Google広告は、「運用型広告」と呼ばれます。これは、一度設定したら終わりではなく、継続的にデータを見ながら改善(運用)していくことで、成果を高めていく広告という意味です。
しかし、「継続的な改善」と聞くと、運用リソースに不安を感じるかもしれませんが、毎日管理画面に張り付く必要はありません。重要なのは、現実的で継続可能な「改善サイクル」の仕組みを作ることです。
例えば、「毎週月曜の朝30分だけは、Google広告の改善に充てる」と決めておくという方法があります。時間が十分に確保できないのであれば、下記の3つのポイントをまずは確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検索語句レポートの確認 | ユーザーが実際に検索した言葉を確認し、自社の顧客ではない無関係な語句を除外キーワードに登録する。広告費の無駄遣いを防ぐ。 |
| 成果の確認 | コンバージョンに繋がっているキーワードや広告文を確認する。成果が出ていないのに費用がかさんでいるキーワードは停止する。 |
| 予算の進捗確認 | 設定した日予算が想定通りに使われているかを確認する。機会損失や無駄な消化がないかチェックする。 |
まずは、無理のない範囲で定期的に広告と向き合う習慣を作ることが、重要です。
3.7 成果指標(KPI)の明確化と入札戦略の理解
「広告の成果を正しく評価するための基準(KPI)」を決め、その目標を達成するためにGoogleのAIにどう動いてもらうか(入札戦略)を選択することで、広告の効果を高められます。
KPIを決定する
広告の成果を測る代表的な指標に「CPA」と「ROAS」があります。どちらを選ぶかは、ビジネスの形によって決まります。
| 指標名 | 定義 | 式 | 向いているビジネス | 目標設定の例 |
|---|---|---|---|---|
| CPA (CostPerAction) |
1件のコンバージョンを獲得するためにかかった費用 | 費用÷コンバージョン数 | 問い合わせや資料請求など、すべてのコンバージョンの価値がほぼ同じ場合 | 「CPAを5,000円未満に抑える」 |
| ROAS (ReturnOnAdSpend) |
広告費に対して、どれだけの売上があったかを示す割合 | (コンバージョン値÷費用)×100% | ECサイトなど、商品によって価格が大きく異なる場合 | 「ROAS500%を達成する」(広告費10万円で50万円の売上) |
例えばECサイトでCPAを目標にしてしまうと、GoogleのAIは利益の少ない安い商品をたくさん売ろうとしてしまい、結果的に儲からない、という事態に陥る可能性があります。
ビジネスの利益に直結する指標を選ぶことが重要です。
KPIを「入札戦略」に反映する
入札戦略とは、設定した目標(KPI)を達成するために、GoogleのAIがクリック単価を自動で調整してくれる機能です。代表的なものには以下があります。
| 入札戦略 | AIへの命令内容 | こんな場合におすすめ |
|---|---|---|
| クリック数の最大化 | とにかくサイトに来る人を増やす。 | 広告を始めたばかりで、まずはデータやアクセスを集めたい場合。 |
| コンバージョン数の最大化 | 予算内でコンバージョンを一番多く取れるようにする。 | 目標CPAはまだ分からないが、とにかくコンバージョンが欲しい場合。 |
| 目標コンバージョン単価(tCPA) | 一定のコンバージョン単価を超えないようにコンバージョンを増やす。 | 目標とするCPAが決まっている場合。 |
| 目標広告費用対効果(tROAS) | 設定したROASの範囲で売上を最大化する。 | 広告費に対する売上目標が明確なECサイトなど。 |
これらの自動入札を機能させるには、AIが学習するためのデータ量(コンバージョン数)が必要です。目安として、過去30日間に30〜50件のコンバージョンデータがあると、AIを使った広告配信として理想的です。
入札戦略の選択は、AI操縦の「モード」を選ぶようなものです。「とにかくスピード重視(クリック最大化)」なのか、「燃費最優先(目標tCPA)」なのか、ビジネスのゴールに合わせて最適な操縦モードを選びましょう。
第4部:【実例】サンゼンデザインが制作したランディングページ
【実例①】北九州の伐採会社様のGoogle検索キャンペーン・ディスプレイキャンペーン

- 検索キャンペーン
- ディスプレイキャンペーン
ターゲット
北九州の会社様(BtoB)
配信エリア
北九州近郊
広告メッセージ
他社で断られた難しい伐採もご対応/北九州近郊で伐採実績1,000件以上/伐採20,000円~
経緯・ポイント
高度な技術と経験を持っている伐採業者様で、危険な条件や環境下での作業が可能。そのため、大手企業様との取引実績があることが特徴です。
BtoBがメインターゲットとなるため、カッチリとした信頼できる企業感を重視したデザインを採用し、樹木伐採や造園という業種から「和の雰囲気」を加えました。
コーポレートサイト(企業紹介サイト)が先行して完成していたため、その内容を踏襲しつつLPとして要点を簡潔にまとめ作成しました。
CVが多く発生し、数十万円から数百万円の受注まで至っているLPです。
参考リンク:https://www.sanzen-design.jp/works/w7131
【実例②】福岡市・北九州市の法律事務所様のGoogle検索キャンペーン・ディスプレイキャンペーン

- 検索キャンペーン
- ディスプレイキャンペーン
ターゲット
福岡の借金問題に悩んでいるユーザー(BtoC)
配信エリア
福岡県近郊
広告メッセージ
借金問題の弁護士相談/相談料0円/即日取り立てストップ/豊富な解決実績
経緯・ポイント
広告出稿1日目でコンバージョンが多数発生したランディングページです。
弁護士に相談することで借金ゼロまたは借金が減額になること、相談料が0円、豊富な解決実績があることなど、お客様の強みを前面に打ち出し、ユーザーの悩みに寄り添った構成で制作しました。
参考リンク:https://www.sanzen-design.jp/works/w7131
【実例③】福岡県の廃油回収会社様のGoogle検索キャンペーン

- 検索キャンペーン
ターゲット
廃油回収をしてほしい事業主様(BtoB)
ターゲット
福岡県近郊
広告メッセージ
廃油の買取/明朗会計!高価買取!/福岡の廃油回収
経緯・ポイント
新たに廃油回収の事業を開始するにあたり、過去の経験からホームページの重要性を感じられていたご代表が集客やSEOに強いホームページ制作会社を探され、当社にお問い合わせいただきました。
当初「廃油の無料回収」をアピールしていましたが、広告出稿のタイミングで「廃油買取」に変更して広告配信。コンバージョンが多く実際の買取に繋がっているため、広告継続をしていただいているランディングページです。
参考リンク:https://www.sanzen-design.jp/works/w6125
第5部:【実践】Google広告の導入を後押しする具体的なアクション
理論と戦略を学んだら、次はいよいよ実践です。このセクションでは、以下の二つの具体的なアクションと、将来的な運用体制を考える上での重要な判断基準を提示します。
- 「スモールスタート」の始め方
- 自分で運用vs代理店に依頼:判断基準とコストを徹底比較
5.1 「スモールスタート」の始め方
Google広告を始めるにあたっては、いきなり大きな予算を投じるのではなく、少額のテスト予算で始める「スモールスタート」という方法があります。失敗のリスクを最小限に抑えながら、ビジネスにとって何が有効かという貴重なデータを手に入れることができます。
具体的な手順は以下の通りです。
- テスト予算を決める
まずは、たとえ成果がゼロでも事業に影響のない範囲で、最初の1ヶ月のテスト予算を決めましょう。例えば、3万円〜5万円程度が現実的なラインです。この予算は「売上を上げるため」ではなく、「データを買うため」の投資と位置づけます。 - キャンペーンを1つに絞る
あれもこれもと手を出すと、データが分散して何が効果的だったのか分からなくなります。まずは最も成果の出やすい「検索キャンペーン」1本に集中しましょう。 - キーワードを5〜10個に厳選する
あなたのビジネスにとって、最も目的に合致した確度の高いキーワードを5〜10個だけ選びます。マッチタイプは「フレーズ一致」または「完全一致」に設定し、無駄な表示を徹底的に防ぎます。 - シンプルな広告文を2〜3パターン作成する
キーワードとの関連性を第一に考え、ユーザーのメリットが明確に伝わる広告文を2〜3パターン作成します。A/Bテストを行い、どちらのクリック率が高いかを見極めます。 - コンバージョン計測とランディングページを再々確認する
広告を配信する前に、テストコンバージョンを行い、計測が正しく機能することを必ず確認してください。ランディングページの準備も万全にしておきましょう。 - 配信を開始し、2週間は「待つ」
配信を開始したら、最低でも2週間は大きな変更を加えず、データが蓄積されるのを待ちます。GoogleのAIが学習するための時間を与えることが重要です。
このスモールスタートを通じて、「どのキーワードでクリックされるのか」「実際のクリック単価はいくらくらいか」「コンバージョンは発生するか」といった、あなたのビジネスにおけるリアルな市場感覚を掴むことができます。
5.2 自分で運用vs代理店に依頼:判断基準とコストを徹底比較
スモールスタートで手応えを感じた後、本格的な運用を考えたときに直面するのが、「このまま自分で運用を続けるか、プロである代理店に依頼するか」という選択です。どちらが良い・悪いということはなく、事業の状況や目標によって最適な選択は異なります。
以下に、それぞれのメリット・デメリットをまとめました。冷静に比較検討し、ご自身の状況に合った選択をしてください。
| 項目 | 自分で運用(インハウス) | 代理店に依頼 |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
| コストの目安 | 広告費実費のみ | 広告費+運用手数料(広告費の20%前後が相場) |
| こんな人におすすめ |
|
|
まとめ
Google広告の本質が「ユーザーとビジネスを結びつけるマッチングシステム」であり、掲載順位が「お金」だけでなく「品質」で決まる公平な仕組みであることを理解していただけたと思います。
「費用対効果」の面では、漠然とした不安を抱えるのではなく、目標から逆算して必要な「投資額」を算出する思考法を学びました。
「種類」の面では、あなたの目的に合わせて最適な広告を選ぶことで、最短距離で成果に繋げられることを確認しました。
「運用」の面では、7つのポイントを押さえることで、無駄な広告費をなくす具体的な方法を知りました。
しかし、日々の業務に追われる中で、これらの施策を質の高いレベルで、かつスピーディーに実行するのは難しいと感じられた方も多いのではないでしょうか。
もし「施策の方向性は正しいか」「限られたリソースで効果を最大化するにはどうすればいいか」とお悩みでしたら、一度専門家の視点を取り入れてみることをおすすめします。
サンゼンデザインでは、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案する無料のWeb集客相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
さらに!
Google広告とYahoo!広告、それぞれのリスティング広告の仕組みについて解説している記事もございます。Web広告全般への理解を深めるために、ぜひ以下の記事も併せてご確認ください。
リスティング広告大全!読むだけでリスティング広告のプラットフォーム・メリット・デメリット・できることが理解できる!
この記事では、リスティング広告の基本から応用までを網羅的に解説しています。特に、Google広告とYahoo!広告の主要なプラットフォームについて、その特徴や違いを分かりやすく説明。さらに、リスティング広告を始める上で知っておきたいメリット・デメリット、そして広告を通じて実現できる具体的な目標についても掘り下げています。
- リスティング広告の基本的な仕組み: ユーザーが検索したキーワードに連動して表示される広告の仕組みを理解できます。
- Google広告とYahoo!広告の比較: 両プラットフォームのターゲット層、広告フォーマット、ターゲティングオプションの違いを把握できます。
- リスティング広告のメリット: 費用対効果の高さ、即効性、ターゲットの絞り込みやすさなど、ビジネスにもたらす利点を詳細に解説。
- リスティング広告のデメリットと対策: 広告費の管理、競合との差別化、運用に必要な知識など、注意すべき点とそれに対する具体的な対策を紹介。
- リスティング広告で実現できること: ブランド認知度の向上、Webサイトへのアクセス数増加、リード獲得、売上向上など、ビジネス目標達成への貢献度を解説。
Web広告の世界は常に進化しており、効果的な広告戦略を立てるためには、その基礎をしっかりと理解することが不可欠です。この記事を通じて、リスティング広告の全体像を把握し、皆様のビジネスに最適な広告運用の一助となれば幸いです。
